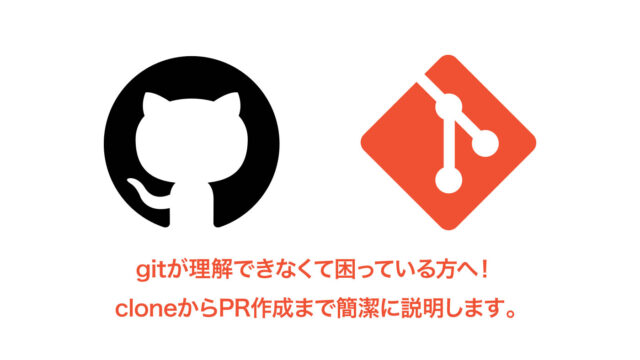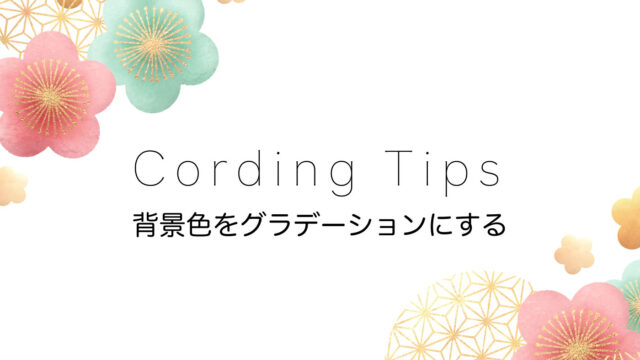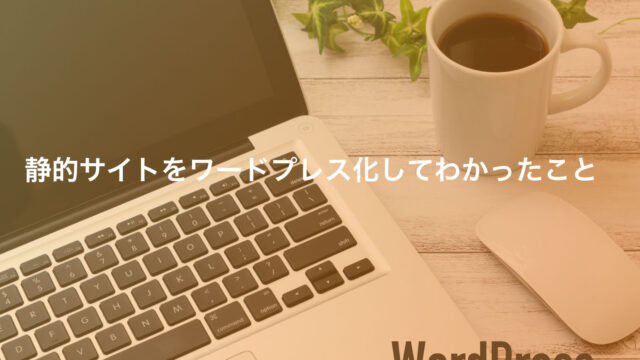こんにちは。sagayuriです。
個人でウェブデザイナーとして活動する上で重要な「契約書」。
みなさんちゃんと契約書を交わしていますか?「知り合いの紹介だから」「友達だから」こんな理由で契約書を交わさないのは危険です。知り合いだからこそ、自分とクライアント両方を守るために必ず契約書を用意しましょう。
とは言え、いざ契約書を用意しようと思ってもどんな内容にしたらいいのか困りますよね。
今回は、わたし的に絶対に記入したいポイントについてご紹介します。
作業範囲、納期を明確にする
まずは作成の目的です。
・どこからどこまでを作業するのか(これがないとどんどん作業が増える恐れも増えるし、追加の作業に対しての費用請求もしづらくなります。)
・制作代金はいくらか
・納期
・対応するブラウザは何か
上記を明確にしましょう。
特に、対応ブラウザについては重要です。
ブラウザによって、デザインの見え方が変わったり、対応していないCSSがあったりするので、どのブラウザで確認したいのか、事前に共有しましょう。全部作ってからクライアントが仕様にないブラウザで確認して、表示が崩れてると問題になった…なんてことが無いようにしたいですね。ブラウザについて知らないクライアントもいるので、シェアの大きいブラウザをこちらから提案してもいいですね。
また、作業範囲については、別途仕様書を用意して、「別途用意した仕様書に基づき作業を行う」などと記載するといいです。
作業が進んでから「こんなはずじゃなかった」とならないように、きちんと仕様書を作成して内容について合意するようにしましょう。
仕様書に記載したいもの
仕様書にはどんな内容を入れればいいでしょうか。
私は以下の内容を記載してます。
- サイトマップ
- ワイヤーフレーム
- 記入してもらったヒアリングシートに基づく納期、対応ブラウザ、対応デバイスなど
- フォームやCMSなどの組み込みの有無
他にも案件によって必要に応じて増減しますが、必ず入れるのは上記の項目です。
検収についてのルール決め
続いて検収についてです。検収とは、完成したものをクライアントが確認する作業を指します。
検収に関するトラブルの例
「クライアントに検収を依頼したが、忙しいなど理由をつけていつまでも確認してもらえず費用を支払ってもらえない」
「クライアントにサイトの検収を依頼したが、当初の仕様書にない機能が不足していると言われて、作業のやり直しをしている」
上記のように、研修が終わらなくて料金を支払ってもらえない事例も割とよくありますので、検収についてのルールは明確にしましょう。
検収について記載するポイント
契約書に検収について記載するときは以下のポイントを意識しましょう。
検収期間を設ける
検収依頼後何日以内に確認して欲しい旨を記載すること
検収の基準を設ける
仕様書に基づいて作業を行い、仕様書に基づいて検収を行う旨を記載します。
連絡がない場合は検収合格とする旨を記載すること
検収を依頼したのに連絡がなくても困らないように、一定期間設定した検収期間内に返事がない場合は、検収合格となる旨を記載しましょう。
入金について
Web制作において、どのタイミングで料金が支払われるのかはとても重要です。支払いに関することも、確実に契約書に盛り込みましょう。
着手金について
会社によって作業開始時に着手金を全費用の何%かを前払いする場合と全て作業が終わってから全額入金する場合があります。できれば着手金として何割かを前払いしてもらった方がいいでしょう。料金の未払いや、作業がある程度進んでからのキャンセルなどを防ぐためです。あとは、ある程度料金をいただいている方が、作る側としても責任感が生まれます。
支払い時期を明確にする
納品、検収が完了したらいつまでに料金を支払う必要があるのかを記載しましょう。(納品後、◯○日以内に支払う、など)
入金時期を明確にしておかないと、ちゃんと料金が支払われるかどうか、不安を抱えながら作業することになりますので、気をつけたいポイントです。
著作権について
著作権についての重要なポイントは次の通りです。
「制作に関する費用が全て支払われるまでは、制作物の著作権は作成者側にあり、料金を全て支払ってからようやくクライアントに著作権が渡る」
この内容を明記することにより、料金を支払われずにずっとサイトを使われ続けることを未然に防ぐことができます。
遅延損害金について
遅延損害金とは、クライアントが本来の支払い期限を過ぎている場合に制作会社が請求できる費用のことです。できれば使いたくないですが、ここもきちんと抑えておきましょう。
契約書に記載がなくても遅延損害金を請求できる
実は、契約書に記載が何もなくても製作側が遅延損害金を請求することができます。契約書に遅延損害金の利率の記載が無い場合は「年6%」と法律で決まっています。
ただ、実際に年率6%だと、クライアント側にペナルティ要素が薄いので、契約書で利率を自分で明記した方がいいです。
では利率どれくらいがいいの?となった場合、法律上制限はありませんが「利息上限法」と合わせて、上限の「21.9%」とするのがいいでしょう。
遅延損害金の記載のポイント
遅延損害金についての注意事項は以下の2点です。
・クライアントからの支払いが遅れた時に、遅延損害金を請求することができる旨を記載すること
・遅延損害金の利率を定める(もし記載がなくても、遅延損害金の請求は可能)
クライアント都合の解約について
Web制作の途中で、急に解約されてしまう場合があります。その時に料金の未払いを防ぐために、解約についてのルールも明記しましょう。例えば、以下のような文章を記載すると良いでしょう。
第●条
甲がウェブサイト完成前に本契約を解約し、または甲の都合によりウェブサイトの制作を中断するときは、乙に対し、解約または中断の時点におけるウェブ制作の進捗に応じたウェブ制作代金を支払わなければならない。また、解約により乙に発生した損害を賠償しなければならない。
このように明記しておけば、料金未払いトラブルを防げます。(できれば途中解約されずに最後まで終えたいですね…。)
弁護士に確認してもらう「リーガルチェック」
どれほど注意深く契約書を作成しても、どうしても抜け穴を防ぐことは難しいものです。
多少コストが掛かっても、作成した契約書は専門家の弁護士などに確認してもらうと良いでしょう。この一手間が、将来のトラブルを防ぎます。
長くなってしまいましたが、今回は契約書についてご紹介しました!契約書は自分を守るために、クライアント双方が気持ち良く仕事をする上で絶対に必要です。必ず用意しましょうね。